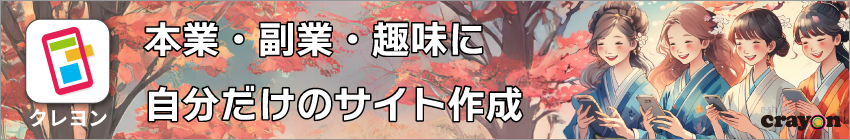
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
2月15日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
女声・童声 2人 テナー 2人 ベース 2人 計 6人
主な練習内容
男声練習 0223の曲。「ブルーシャトウ」「イエスタデイ」「北酒場」。通して録音してみました。
混声練習10:00〜11:50
「恋の季節」「雨上がり」「フニクリフニクラ」
「夢の中へ」「世界が一つになるまで」を歌いました。
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
2月11日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
女声・童声 2人 テナー 2人 ベース 2人 計 6人
主な練習内容
男声練習 「ブルーシャトウ」「イエスタデイ」「北酒場」。
混声練習
体操+発声練習(2人で聴き合う、3人でドミソ練習) 「恋の季節」」「夢の中へ」「雨上がり」「フニクリフニクラ「世界が一つになるまで」を音取り・確認後、歌いました。
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
2月1日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
女声 3人 テナー 2人 ベース 2人 計 7人
主な練習内容
男声
「ブルーシャトウ」「イエスタデイ」「北酒場」。
混声
「フニクリフニクラ」「夢の中へ」「世界が一つになるまで」。どの曲も久しぶりに歌うので、リズムや音を確かめながら、合わせました。
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
1月25日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
女声 2人 テナー 1人 ベース 2人 計 5人
主な練習内容
男声練習 0223の曲。「ブルーシャトウ」「北酒場」衣装の話し合い・当日の集合時刻を決めました。
混声練習10:00〜11:50
体操+発声練習(2人で聴き合う)。「雨上がり」音取り最後まで。「恋の季節」「手のひらを太陽に。「にじ」も歌いました。
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
1月18日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
女声・童声 7人 テナー 2人 ベース 2人 計 11人
主な練習内容
男声練習 0223の曲。「ブルーシャトウ」「イエスタデイ」「北酒場」カッコいい歌い方を少し工夫してみました。
混声練習
体操+発声練習(2人で聴き合う、3人でドミソ練習)。「恋の季節」「手のひらを太陽に」「雨上がり」の音取り。最後に「にじ」も歌いました。
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
1月11日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
女声・童声 2人 テナー 1人 ベース 2人 計 5人
主な練習内容
男声練習 0223の演奏予定曲。「ブルーシャトウ」「北酒場」の音取り確認。
混声練習
新しい編成の試み、第一弾としてお試しでピンキーとキラーズの「恋の季節」を歌ってみました。「雨上がり」「手のひらを太陽に」の音取り・確認。
おまけの話
「恋の季節」を歌ってみました。アカペラで、いずみたくの曲を扱うのは「手のひらを太陽に」に続いて二曲目かな? Voice Vox では「女ひとり」を歌っていたっけ。
「恋の季節」は、体験的音楽論に書かれているように、黒人霊歌のスタイル=コール&レスポンスを取り入れた曲です。
しかし、大ヒットしたことでも自明の通り、誰にでも口ずさめるリズムとメロディーが昭和世代には嬉しい。
いずみたくさん自身がうたごえ運動に関わり、本来的な意味でのフォークソングを志向していたことと歌いやすさは繋がっていると思う。
歌いやすさは同時に聴きやすさでして、練習量の割には、お客様の反応がない曲よりも、誰もが聴いたことがあるような楽しい曲を発信していきたいと思います。
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
12月21日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
テナー 2人 ベース 2人 計 4人
主な練習内容
2025年最後は、男声部VoiceVoxの練習。新曲「ブルーシャトウ」と「北酒場」の音取り。VoiceVoxは来年2月23日に港南区音楽交歓会への参加を予定しているのですが、「ブルーシャトウ」「イエスタデイ」「北酒場」の三曲を歌うことにしました。
おまけの話
ハーモニーを探し求めて50年〜自伝風に。その15
お江戸コラリアーず
ボクにはフルタイムの仕事を終えたら、始めたいことがありました。その一つが港南台アカペラシンガーズです。皆様今日まで本当にありがとうございます。
今もそうなのですが、一度にたくさんの活動に関わると言うのは、なかなか調整に苦労するものです。ヘンデル室内合唱団は港南台アカペラと練習時間が重なり退団させていただきました。
自伝風に履歴を書き連ねていますが、一度もボクが経験してこなかったのが、コンクール出場。技術水準に関してしのぎを削っている合唱団をボクは経験してこなかったのです。すでに還暦を超えていたボクを受け入れてくれる合唱団を探し始めました。(コンクールに出ている団体は年齢制限を設けているところが多いのです)
ボクは2017年の6月、大学グリーの還暦ステージというイベントがあり、同期を中心とした40名くらいの男声合唱を指揮しました。その打ち上げイベントで顔見知りだった現役グリー指揮者の村田さんを見つけ、「今度おえコラに見学に行ってもいいですか?」と聞いてみると、「どうぞ」との返事。
早速練習した会場に行ってみると、明らかにボクの教わってきた発声では、音も音色も合わないことが、その場でわかりました。当時高島みどりの「落下傘」を歌っていて、セカンドのパートソロがあるのですが、その音の揃い方はさすがの水準でした。これがコンクールで評価するされる水準なのかと、驚いたわけです。
できそうもない、合わない→退却という選択肢がボクにはありません。経験したことがないからこそ、やれるところまでやってみるで、合唱団を続けてきたのですから。
おえコラの初ステージは、池袋の東京芸術劇場、合唱コンクールの全国大会でした。その後おえコラといっしょに全国コンクールには3回出ました。中でも札幌大会で歌った三善晃の「縄文土偶」は凄い演奏になり、やはり三善晃作品の「王孫不帰」と共に、強烈な思い出になっています。
その時、その仲間といっしょにいたからこそ、チャレンジできた曲がたくさんありました。
こんなことを書きながら、2025年2月の仙台演奏旅行以来、自治会活動の影響で、おえコラ練習に通うことができていません。メンバーに復帰できるのか、一ファンとして聴きにいくことになるのか、この先どうなるでしょう?
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
12月14日杉田劇場ホール
第5回みんなの音楽会
本日の参加者数
女声 4人 テナー 2人 ベース 2人 計 8人
本日の活動内容
杉田劇場で男声→混声の順にステージ練習
磯子の社会教育センターに移動して補充練習。
13:30〜 第5回みんなの音楽会。
男声VoiceVoxは、「ヘルプ」 「アンド アイ ラヴ ハー」「イエスタデイ」「オブラディオブラダ」を演奏。
混声は「いっしょに」「にじ」「涙のリクエスト」を演奏しました。
おまけの話
ハーモニーを探し求めて50年〜自伝風に。その14
ヘンデル室内合唱団
さかえ男声のご縁で誘われて、入れていただいたのがヘンデル室内合唱団。金川明裕先生のご指導のもと、ルネサンス・バロック音楽を中心に歌っている合唱団です。
ここでの初体験は二つ。一つは入団時にオーディションがあったことです。そんな試験があるとはびっくりで、港南台アカペラでも歌ったことがあるバッハのコラールを初見で歌いなさいと言うのです。何だか大変なところへ来てしまったという第一印象でした。
でも大変なことはまだ続きます。
モンテヴェルディの名曲「アリアンナの嘆き」。この曲は5声なのですが、先生によると上から三つ目はカウンターテナーが受け持つと言うのです。カウンターテナーなんて、できる人いるかなぁとたかを括っていたら、何とそれはボクをご指名だったのです! 驚天動地とはこのこと。
元々はバリトンのボクが、ずっと五線譜に収まらない高い音を歌うのですから、結構大変でした。おかげさまで高い音に対する恐怖感は和らいだ気がしますが。
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
12月7日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
女声・童声 3人 テナー 2人 ベース 2人 計 7人
主な練習内容
男声
「ヘルプ」のテンポを弛まないように。「アンド アイ ラヴ ハー」中間部のバランス。最後にトップのボクが加わり、バランスを調整する。「イエスタデイ」why she〜 ベースとドトップのバランス調整。
混声
「いっしょに」母音唱naで歌い、音色を揃えてとけあう練習。
「にじ」短縮版。アルトパートの練習。
「涙のリクエスト」いきなり2番かっこへ行き演奏時間短縮。
おまけの話
ハーモニーを探し求めて50年〜自伝風に。その13
横浜さかえ男声合唱団
転勤先への往復時間や休日出勤の更なる増加によって、ボクは戸塚混声・横浜紅葉丘合唱団の指揮活動の継続、ならびに奥本とも歌曲研究会のレッスンから遠ざかってしまった。
しかし、歌や合唱がない生活というのは、どうにも無味乾燥な感じで、半年後には隙間時間でも活動できそうな合唱団を探し始めていました。
そして入れていただいたのが、横浜さかえ男声合唱団。指導者は堀部隆二先生。先生の発声練習は芸大宮川先生仕込みの「こんにゃく体操」から始まる。昔演劇仲間から教えてもらったことがある野口体操によく似ている。
テナーに変更したボクの初ステージは、何と横浜刑務所だった。幸いなことに刑務所に入ったのは、後にも先にもその一回きりです。演奏を聴いてもMCがユーモアたっぷりに話しても表情ひとつ変えない受刑者の様子がとても印象的でした。
港南台アカペラシンガーズ 練習日誌
11月30日港南台ひの特別支援学校 音楽室
本日の参加者数
女声・童声 2人 テナー 2人 ベース 2人 計 6人
主な練習内容
男声「ヘルプ」 「アンド アイ ラヴ ハー」「イエスタデイ」「オブラディオブラダ」。「ヘルプ」はゆっくり目に音の重なりを感じながら。「アンド アイ ラヴ ハー」は、演奏時間を縮めて、二番かっこ部分中心にを練習ました。4曲を通して録音しました、
混声
「いっしょに」ハーモニーの精度を高めて音がしてとけ合う感じをつかみましょう。「涙のリクエスト」ゆっくりのテンポでリズム合わせる練習をしましょう。
「にじ」も演奏時間を短縮して歌いました。
それぞれ録音して、共有しています。
おまけの話
ハーモニーを探し求めて50年〜自伝風に。その12
奥本とも歌曲研究会
誰についてどのような音楽を教わるか? これはかなり大事な話です。横国グリー時代の田中清隆先生、藤沢男声時代の工藤博先生、この頃一回だけでしたが大久保昭男先生に来ていただいたこともありました。戸塚混声では安達先生や小林菜美先生をお招きしていました。
全て合唱団の表現力を向上させるためのレッスンでしたが、そのうち一人で歌うってどんな世界が広がっているんだろうと体験してみたくなりました。
教員仲間の紹介で通い始めたのが奥本とも歌曲研究会です。
バリトンの独唱者としてステージに立ち、イタリア歌曲やシューベルト、オペラアリアなどを歌いました。
伴奏者と共に一人で表現する音楽は、非常に自由度が高いのですが、同時に発する音が全て自己責任なので、本当は臆病で小心者のボクは毎回ドキドキしながら歌っていました。
歌曲研究会は、横浜紅葉丘合唱団と同様、転勤でレッスンに通いづらくなってしまい、独唱活動から遠ざかってしまいます。
そして、休日に自宅から通える男声合唱団に入れていただいたのです。
その合唱団とは、横浜さかえ男声合唱団。ご指導は声楽家の堀部隆二先生。ボクはこのご近所男声合唱団でトップに転向しました。初めのうちは出したことがない音の高さに喘いでいたのですが、そのうち慣れてくると平気な顔で歌っていました。独唱活動をしていた経験が男声合唱で担当したソロに活かせたように感じます。
その後、発声についてはお江戸コラリアーずで大島博先生から指導を受けています。
バックナンバーの閲覧をご希望の方は、下記URLをクリックするとご覧いただけます。
https://www.dropbox.com/sh/182vkrrq00024xt/AABouaaBYez3IDE3629FekISa?dl=0
※ブログは随時編集を加えているため、バックナンバーの内容が閲覧されている内容と一部異なる場合があります。